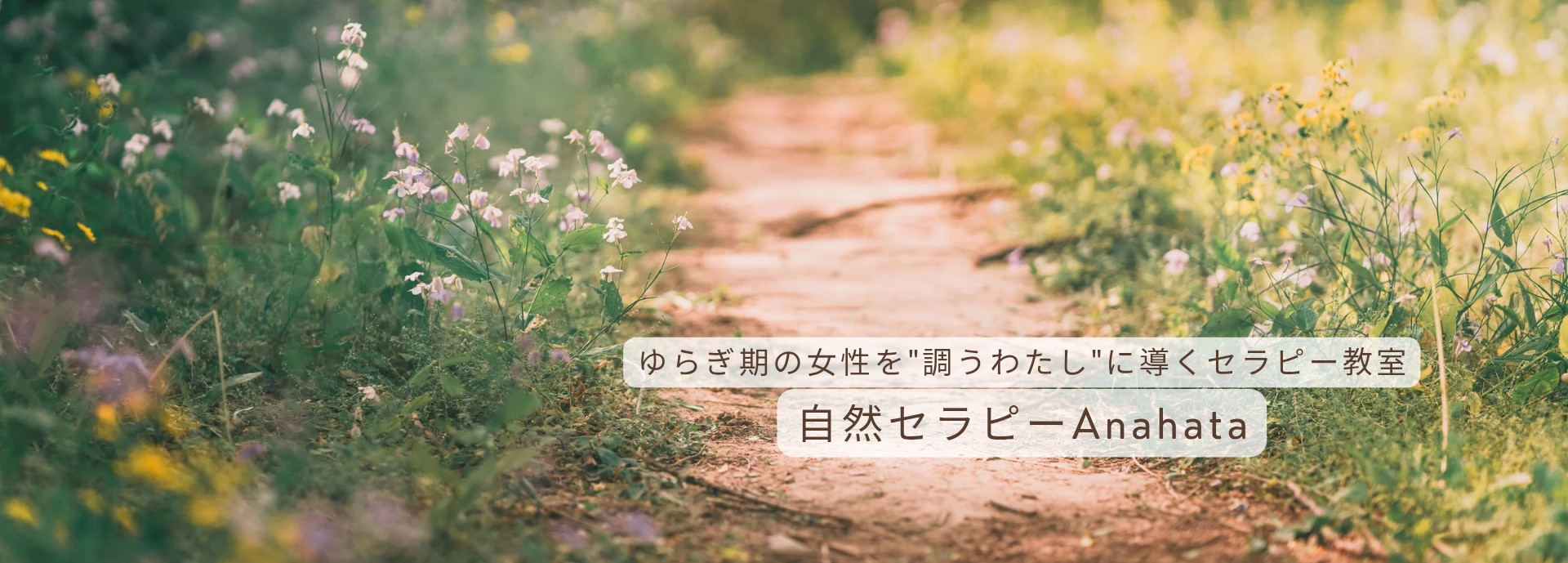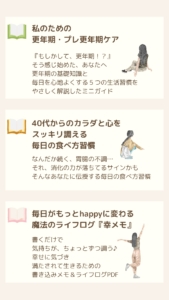旬の味覚【さつまいも】と【落花生】でアンチエイジング&肥満予防

実りの秋、食欲の秋
秋晴れの気持ちの良いお天気が続くようになりました。
先日、富山でもお散歩スポットの公園に行きましたが、どこの駐車場もビックリするくらい満車で止めれず…。
スタバでドライブスルーをして、ドライブして帰ってきました。
さて、そんな秋、anahata農園は実りの秋をむかえました。
といっても、裏庭の小さな農園ですので、わんさか収穫できたわけではありませんが、おうちでしばらく食べれるくらいの、さつまいもと落花生を収穫することができましたので、今回はそのお話になります。
落花生はアンチエイジングと肥満予防に一役かってくれます
皆さん、とれたての落花生は食べたことありますか?
ピーナッツは、どなたでも食べたことがあると思うのですが、落花生の殻をとったものをピーナッツと呼ぶそうな(一緒だと思っていたw)
地域や家庭によっても違うと思いますが、普段そんなに食卓では目にすることのない落花生。
落花生は、日本では千葉が産地で有名ですが、その千葉ではとれたて落花生を生のまま茹でて【茹で落花生】として食べるそうです。
最近、ちょくちょくその様子をTVでも見かけるようになりました。
今年、自然農のanahata農園では、夏野菜のピーマンやナス、トマトの成長のために、マメ科の落花生や枝豆を混植していました。
マメ科の作物は、作物に大切な三大栄養の一つ窒素を土の中で蓄えてくれます。
そうすると、窒素が好きな作物を近くに植えてやると、窒素肥料をあえて外からやらなくても成長が促進。

そういう理由で、数株の落花生や枝豆が実り、ちょうど今落花生の収穫時期になったのですが、どうやって食べてよいかわからず、うちでも千葉の皆さんのマネをして、とれたての落花生を茹で落花生にすることに。
ちなみに、売ってるピーナッツは炒ってあるそうです。
作り方はとても簡単です。
とれたての生の落花生を塩水から茹でて、沸騰してから30-40分ほど茹でます。
そうすると、ピーナッツとは一味違った仕上がりに。
私は、初めての調理でちょっとだけ?塩加減を間違えてしまい、とってもしょっぱくしてしまいましたが😅
塩加減は、水1リットルに対して大さじ1くらいがよい加減なようです。
そのとってもしょっぱくなった落花生は、冷ましてサラダに混ぜて食べるとドレッシングいらずで美味しく食べれて、ほっと一安心。
今日も一株掘り起こすので、今度こそ塩加減は間違わないようにしないとですね😄
落花生には抗酸化ビタミンと不飽和脂肪酸がたっぷり
で本題ですが。
落花生の栄養素ってなんだろう?と考えてもすぐには出てこず。そういえば、「ピーナッツ食べ過ぎると鼻血でるからだめよ。」と言われたことを思い出したくらいでしたが
落花生はピーナッツというくらいなので【ナッツ】の仲間。
そしてナッツの栄養と言えば、ビタミンEや不飽和脂肪酸が代表的です。
以下に、落花生の栄養素を挙げてみました。

不飽和脂肪酸(オレイン酸・リノール酸)
不飽和脂肪酸とは、体内の脂肪を構成する脂肪酸の1つ。植物性の油や魚の油に多く含まれます。不飽和脂肪酸にも種類があるのですが、ここでは割愛させていただきますね。
その中のオレイン酸は、有名なところではオリーブオイルに多く含まれていて、血中のLDLコレステロール(通称悪玉コレステロール)を下げる効果があります。コレステロール値を下げてくれるので肥満予防にもつながるというわけです。
リノール酸もニュアンスとしては似たような効果があって、動脈硬化や、血栓と呼ばれる血の塊が血液内でできてしまうのを防いでくれます。また、血圧降下やLDLコレステロールを下げることにも一役かってくれます。
そのオレイン酸とリノール酸を含む落花生にも同様の効果があるというわけです。
ただし酸化しやすいので、揚げ物や炒め物などの高温調理にはあまり向きません。
ビタミンE
こちらは、抗酸化ビタミンとして有名なビタミンE。抗酸化ビタミンとは体内で作られる過剰な活性酸素の働きを抑える作用を持つビタミン。
酸化ストレスによる、老化、がん、生活習慣病などの予防につながります。お肌にとってはシミ、しわの予防効果もあり、老化を防ぐアンチエイジングに効果があります。
(※活性酸素とは・・・人間は呼吸によって取り込んだ酸素を利用して生命の活動を維持しています。取り込まれた酸素の一部(数%)は通常よりも活性化された活性酸素に変化して、体内の代謝過程での反応や免疫機能として働くという大切な役割をしていますが、過剰に産生された活性酸素は、人間の細胞を傷害して、がん、心血管の疾患や生活習慣病など様々な疾患をもたらす要因となってしまいます。)
ナイアシン
ナイアシンとは水溶性ビタミンB群の1つで、ニコチン酸とニコチンサンアミドの総称。これらは体内での酵素の働きを補助する補酵素の役割をしていて、代謝やエネルギー産生、脂肪酸や体内ステロイドホルモンの生成に関与しています。
落花生は、代謝やエネルギー産生に関わっているこれら栄養素も含むので、ダイエットなどにも効果を発揮してくれそうですね。
またアルコールを分解するために必要な栄養素でもあり、二日酔いの予防にもなります。
ミネラル
体内の余分な塩分を排出しむくみを取ってくれるカリウム、骨や歯を形成するリン、リンやカルシウムとともに骨を形成し代謝を助けるマグネシウム、貧血予防してくれる鉄などが含まれています。
落花生の代表的な栄養素を挙げましたが、最後に1つ。落花生は他のナッツ同様、カロリーも高い食品ですので、くれぐれもとりすぎには注意しましょう。
さつまいもの疲労回復、美肌、便秘解消効果でさらに美しく
そして、実りの秋の代表格といえば【さつまいも】
anahata農園では、3年ぶりに育てました。

どうっして3年ぶりにかというと、ちょうどその頃、収穫したさつまいもを古家の物置で追熟していたら、ネズミの被害にあいまして。
まあ、小さめのおイモでも結構沢山あったんですが、綺麗さっぱり持っていかれました…。食べカスすら残さずにです。
その時のショックといったら、立ち直れないほどで…というのは大げさですが、以来なんとなく育てる気にならず、今日まで至りました。
今年は、久しぶりに植えてみようと、小さな畝一つ分、4株のさつまいもを植え、出来栄えは上々。
さつまいもは、収穫後の追熟で甘みが増して、とても美味しくなります。
通常2週間くらいと言われていますが、紅はるかという品種は3週間くらいは追熟したほうがよいようです。
収穫から1週間たち…あと2週間。
追熟完了が待ちきれない今日この頃。
そんな、煮ても焼いてもスイーツでも美味しい【さつまいも】ですが、こちらも嬉しい栄養素たっぷり。
では、さつまいもの栄養を見ていきましょう。
ビタミンC
ビタミンCは、シミ予防による美肌効果、疲労回復や風邪予防に効果があります。ビタミンCは水溶性ビタミンと言って、加熱によって壊れやすいものですが、サツマイモの場合、含まれるデンプンが過熱から守ってくれる働きをするので、加熱調理しても摂取できるというすぐれものです。
ただ体に過剰な分は尿として排泄されてしまうので、たくさん摂っても効果は期待できません。
食物繊維
食物繊維を含みますので、便秘に効果が期待できます。
ヤラピン
こちらはあまり聞いたことのない成分ですが、サツマイモを切るときに出る白い液状の物質のことで、古くから緩下剤として使用されてきたようです。食物繊維との相乗効果で更に便秘の改善と予防が期待できますね。
ビタミンE カリウム
落花生の所で詳細を触れましたが、ビタミンEは、体内の活性酸素の過剰による老化や生活習慣病を防ぎシミ・しわ予防といったアンチエイジングの効果が期待できます。
またカリウムも、体内の余分な塩分を排出し、むくみを取ってくれ、また血圧を下げてくれる効果が期待できます。

以上、今回のブログでは、秋の味覚の落花生とさつまいもの栄養素についてみてきましたが、作って収穫した作物の栄養を改めて見てみると、日ごろ何気なく美味しいと思って食べていますが、人間の体に大切なものが沢山含まれていることを実感しますね。
食って大切です。
(参考文献)